小学6年生の夏休みが終わり、いよいよ過去問演習が本格化する時期ですね。
志望校合格への道筋をつくる重要な教材である「過去問」。ただ解くだけではもったいない!忙しい毎日でも、効果的に活用するためのポイントと具体的な実践方法をお伝えします。
ポイント1:過去問は「弱点発見」と「傾向分析」のための地図
過去問は、お子さんの今の実力を測るためのものではありません。むしろ、志望校がどんな力を求めているのか、そしてお子さんがどこを重点的に対策すべきかを教えてくれる「道しるべ」です。
【活用例】
- 保護者の方が主導で分析する:お子さんに任せきりにせず、保護者の方が過去問から出題傾向(頻出分野、形式など)を読み解き、お子さんと共有しましょう。「この学校は図形問題がよく出るね」「記述問題が多いから、対策が必要だね」など、具体的な声かけが効果的です。
- 合格最低点とのギャップを可視化する:過去問の点数だけを見て一喜一憂するのではなく、合格最低点との差を把握しましょう。その差を埋めるために、どの教科に力を入れるべきか、具体的な学習計画を立てるヒントになります。
ポイント2:本番を意識した「時間と環境」のセット
本番で実力を最大限に発揮するためには、過去問演習の段階から入試と同じ状況を再現することが大切です。
【活用例】
- 本番通りに時間を設定する:各教科の試験時間を厳守するのはもちろん、慣れてきたら本番より5分短い時間で解くなど、少し負荷をかけてみましょう。
- 解答用紙を本番サイズにコピーする:問題用紙は原寸大、解答用紙は必ず原寸大に拡大コピーして使いましょう。特に記述問題や計算スペースの感覚に慣れることが重要です。
- 本番と同じ時間割で4教科通しで解く:入試当日と同じように、朝から4教科を休憩時間も挟んで通しで解いてみましょう。長丁場の集中力や体力配分を養う練習になります。
ポイント3:解き直しは「間違えた原因」の徹底分析
過去問は、解いて採点して終わりではありません。最も大切なのは、「なぜ間違えたのか?」を徹底的に分析することです。
【活用例】
- 「解き直しノート」を作る:間違えた問題は、解答を写すだけでなく、「ミスした理由(計算ミス、知識不足など)」と「次にどうすれば正解できるか」を具体的に書き込みましょう。
- 「復習サイクル」を回す:一度間違えた問題は、時間を空けてもう一度解き直しましょう。2〜3日後、遅くとも1週間以内に解き直すことで、知識が定着しやすくなります。
- 保護者が「メンタルケア」を担う:点数が悪かったとしても、「よく頑張ったね」「ここを直せば次はもっと良くなるよ」と、努力を認める声かけを心がけましょう。お子さんの精神的な負担を減らし、次の学習へのモチベーションにつなげることが大切です。
過去問は、志望校合格への最後の追い込みをかけるための最高の教材です。忙しい毎日の中でも、これらのポイントを押さえて、お子さんと二人三脚で乗り越えていきましょう。
今日も、一歩前へ。
では、また。
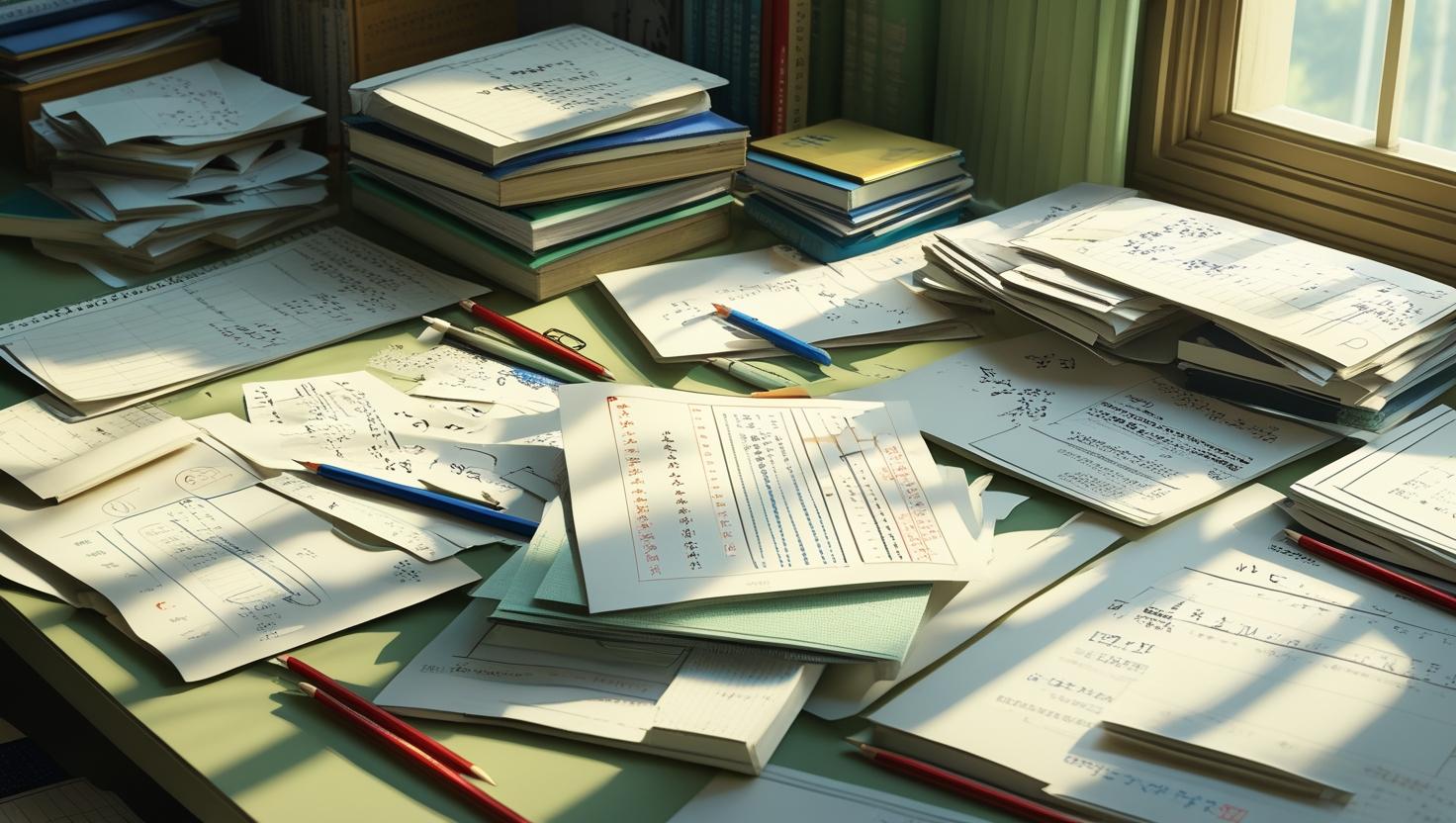
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c9b77.6667e184.203c9b78.fc415b23/?me_id=1213310&item_id=21235871&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0408%2F9784478120408_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント